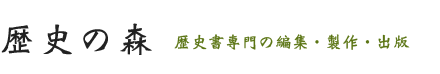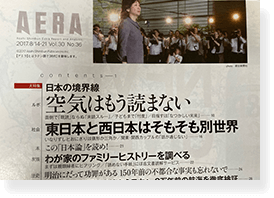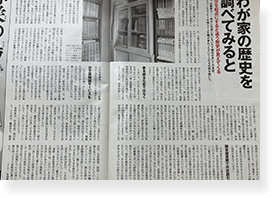古記録資料の
解読
ご所蔵の古記録・古文書の解読サービス
古記録資料の解読サービスでは、「釈文(活字化)」「読み下し」「現代語訳」を承ります。解読をご希望の方は、まずは無料のお見積もりをお申し付けください。下記3パターンでご対応可能です。
- パターン1
- 「釈文」のみ
- パターン2
- 「釈文」+「読み下し」
- パターン3
- 「釈文」+「読み下し」+「現代語訳」

- 用語解説
-
- ▶ 釈文(資料に書かれている文字を現行漢字を用いて活字に直す)例)古天地未剖、陰陽不分
- ▶ 読み下し(原文を読み易く書き直す)例)古に天地未だ剖れず、陰陽分れざりしとき
- ▶ 現代語訳(現代文に訳す)例)昔、天地も未だ分かれず、陰陽の対立も未だ生じなかったとき
※日本古典文学大系『日本書紀』上、岩波書店、1967年より引用
下記へ、納品後に頂戴した身に余る御礼の一部を紹介いたします。
- 「おかげさまで、我が家の歴史がついに日の目を見た感じがします。ある意味人生の大きな一ページになるかもしれません。本当にありがとうございました。」(K・Mさま)
- 「大変分かりやすい現代語訳に解読していただきまして感謝致しております。昭和初期にこんないきさつがあったのかと初めて知る内容にびっくりしております。本当に助かりました。ありがとうございました。」(M・Yさま)
- 「早速、実家の祖母に資料を見せたところとても丁寧に翻訳・調べていらっしゃると大変喜んでおりました。また、機会がございましたら是非とも宜しくお願い致します。」(T・Kさま)
対象となる資料について
お受けできる資料の例
- ●崩し字で書かれた文字資料
- いわゆる「古文書」に限らず、明治時代以降に書かれた手紙や個人的な記録などもお受けいたします。
お受けできない資料の例
以下のような資料は、小社が扱う歴史学の範疇からはずれる資料であり、十分な解読をご提示することが困難であるため、原則としてご辞退させていただいております。また、そのほか、高度に専門的な内容を扱った資料に関しては適切な解釈をご提示できない場合がございます。ご了承ください。
- ●掛け軸などの美術品・骨董品
- ●和歌・漢詩などの国文学資料・漢文学資料や、芸道・武道など専門性の高い内容の資料
- ●他機関等に所蔵の未翻刻の冊子類
ご用命の手順
1資料の送付
資料全体のコピーを小社宛てにご郵送いただくか、デジタルカメラで撮影した画像をメールに添付してお送りください。(合計で2MB以内としてください。)
その際、上記サービス内容
- ・パターン1「釈文」のみ
- ・パターン2「釈文」+「読み下し」
- ・パターン3「釈文」+「読み下し」+「現代語訳」
のいずれをご希望かお伝えください。
また、手順2の書類をお送りするため、必ずお名前・ご住所(送付先)を明記してください。
- ご留意点
-
- ●資料のサイズが大きい場合は、数枚に分けるなどして文字が判読可能な大きさになるように撮影してください。文字が画面外にはみ出さないようご注意ください。
- ●お見積もり用にお送りいただいたコピーは、原則として返却いたしません。返却をご希望の方は必ず返却用の封筒と切手をご同封ください。
- ●お送りいただくコピー・画像データについて
- ・文字が小さすぎたり画像が不鮮明ですと解読に支障が生じます。コピー・画像データを作成される際はなるべく鮮明な画像となるようご留意いただき、画面からはみでる文字がないよう余白に余裕をもってコピー・撮影をおこなってください。また、撮影はなるべく真上からおこなってください。(斜めから撮影すると読み辛い画像となります)
- ・1枚の画面に収まりきらない場合は複数枚に分けてコピー・撮影し、番号を記入する・ファイル名に番号を振るなどして並び順が一目で分かるようにしてください。また、コピー・画像の重複している箇所の一方に×印を付けるなどして、解読が必要な箇所が一目でわかるようにしてください。
- ●お送りいただく資料について、入手経路、言い伝えなどの情報がございましたら、ぜひお知らせください。より正確な解読の手がかりとなる場合がございます。
2お見積書
小社にて解読料金をお見積もりの上、「お見積書」「お申込用紙」をお送りいたします。
- ご留意点
- ●無料でのお見積もりということから、上記書類の送付は手順1が整ったケースに限らせていただきます。
不備な点の個々に関して小社からのご連絡などはいたしません。
3お申込み
ご用命の際は「お申込用紙」に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、FAXか郵便にて小社までご返送ください。
4初期費用ご入金
初期費用(お見積額が税込5万円を超える場合は全額の1割相当額、5万円以下の場合は一律3,000円)もしくは解読料金の全額をご入金ください。ご入金の確認がとれ次第、解読作業を開始いたします。
- ご留意点
- ●入金方法は、郵便振替もしくは銀行振込みです。
ご入金のご連絡をいただかない限り定期的な入金確認をおこなっておりませんので、銀行振込みの場合は必ずご入金予定日をお知らせください。郵便振替はご入金の確認に数日かかります。お急ぎの場合は銀行振込みをご利用ください。
5解読作業
作業期間はご用命の内容と資料の分量によって異なります。
6解読文のお渡し
お見積り料金から、手順4にてお支払いいただいた初期費用を除いた残金をご入金いただき、確認が取れ次第、解読文を発送いたします。全額をご入金済みの場合は解読作業が終わり次第発送いたします。
料金
資料の内容・保存状態など、様々な要因によって解読の難易度やそれに伴う作業量などが大きく左右されるため、ご依頼の資料全体のコピー・写真などを拝見したうえでなければ解読料金をご提示することができません。
400文字を最低分量とさせていただき、それ未満の分量のご用命は一律で400文字相当の料金とさせていただきます。
ご入金後は業務の性格上、お客様のご都合によるキャンセルはご容赦ください。
納品形式
- ●レーザープリンタで普通紙にプリントしたもの、およびその元データ(Word形式)を入れたCD-Rを、郵送にて納品いたします。レイアウトや製本を含むサービスではないことをご了承ください。納品後における資料の内容上のお問い合わせは固くご遠慮願います。
- ●当サービスに関しまして、小社において解読のうえ、納品したものについて出版物等への2次使用は固くお断りいたします。
お受けできない内容
- ▼古記録・古文書の学術的な解説をして欲しい/美術品としての価値を鑑定して欲しい
- 小社の「古記録の解読」サービスは、あくまでも「読めない文字資料」を読み解くサービスです。資料の内容にまで立ち入った解釈や鑑定はおこなっておりません。
- ▼長文のなかの一部分のみを解読して欲しい
- 古記録・古文書は、全体を通して読むことを前提として書かれたものです。 そのため、「文脈を把握しながら全体を通して読めば読める」ことを前提に、大幅に文字の字形を省略して書かれることが多くあります。 そのような場合、その箇所だけを抜き出して読もうとしても困難であるため、結局は全体を通して読まざるをえなくなります。 こうした理由から、原則として一部分のみの解読はお受けできません。
- ▼書いてある内容が分かればいいので現代語訳だけ頼みたい
- 資料の現代語訳を作成する際には、
- 崩し字で書かれている文字を判読し、資料に書かれている通りに活字化する
- それを基に、どう読むのかを判断し読み下し文を作成する
- 読み下し文を基に現代語訳を作成する
- ▼文字が消えかかった資料を復元して欲しい
- 小社には、経年による資料の傷みなどで、物理的に読めなくなっている文字を復元する技術はございません。資料の保存状態によってはご依頼をお受けできない場合がございます。
また、傷みの少ない資料でも、虫喰いや墨の薄い部分があるなど、部分的に判読できない箇所がある場合がございます。
伏字・推定字について
ご用命いただいた資料は極力全文を解読できるよう努めておりますが、どうしても解読できない文字が残る場合があります。
そうした文字を伏字(判読不能の文字があることを□などの記号で示します)や推定字(断定はできないものの、可能性がある文字を示します)の扱いとさせていただく場合があります。
特に、虫喰いにより文字の一部が欠けている場合や、もともと墨が薄かったり保存状態が悪かったりして文字が不鮮明な場合に伏字・推定字が生じやすくなります。